日本の ART 医療の方向性 -10 年後を見据えて-
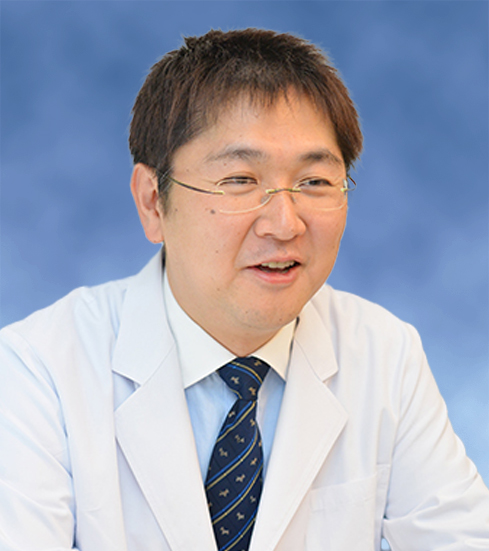
2020年度 年次大会-講演抄録|今後の日本の ART 医療の方向性
学会講師:奥 久人
Abstract
新たな時代(New ERA)のART 医療を予測することは簡単ではない.我々は,急速な進化を遂げてき たART医療の足跡を過去に遡って振り返ることで, 未来へのヒントを見出せるのでは無いかと考えた. 今回の講演では,胚培養室(技術),妊孕能温存治療, 男性不妊治療,調節卵巣刺激法,そしてARTの負の側面としての一卵性双胎や癒着胎盤の予防などにつ いて,過去と現在を比較し,この対比を通して10 年 後のART医療を予測してみた. 「胚培養室(技術)」10年前,加湿型培養庫がところ狭しと並べられていた培養室には,いまやタイムラプス型培養器が整然とならび,胚培養士のワークフ ローは一変した.精液検査はカウンターを用いて目視をしていたが,CASAによる自動検査となっている. 精液調整は遠心分離を必要としない方法にシフトし つつある.Conventional ICSIはPIEZO ICSIにとって代わられつつあり,取り違え防止はマンパワーを活用したダブルチェックからバーコード認証システ ムになった.この10年の進化には目を見張るものが ある.
「一卵性双胎や癒着胎盤の予防」過去10年における 当院の一卵性双胎発生率は1.5%と自然妊娠に比べおよそ2倍の頻度であった.一卵性双胎は早産やTTTS のリスクファクターとなり,周産期予後に悪影響を及ぼす.10年後のARTには一卵性双胎を無くす工夫 が求められる.ARTで発症率が高まると懸念される癒着胎盤も周産期予後を左右する重要な疾患である.当院における過去10年間の凍結胚融解移植後妊娠の 癒着胎盤発症率は1.9%であり,自然妊娠よりも高い ものであった.癒着胎盤のリスク因子を解析するこ とで,10年後のARTではその発症率を下げることができないかどうか考察したい.
「調節卵巣刺激法」10年前,当院ではショート法を 選択するケースが最も多かった.しかし2年前から調節卵巣刺激法は一変し,今やショート法やロング法を選択するケースは非常に少なくなり,主流はPPOS 法となった.このように過去10年で様変わりした調 節卵巣刺激法であるが,さらに10年後のあり方につ いて予測してみたい.
「妊孕能温存治療」卵子凍結による出産は1986年に, そして卵巣組織凍結による出産は2004年に報告され た.今や卵子凍結は確立された治療として認められている.2012年には日本がん生殖医療学会設立,そして2017年には日本がん治療学会がガイドラインを発行するなど,がん患者の妊孕能温存治療は確立しつつあるように思える.この間には,Random-Start やDuo-Stimuなどの卵巣刺激法の工夫もあった.10 年後のあり方についても予測してみたい.
「男性不妊治療」精子の発見は 1677 年に遡る. 1993年には精巣精子による出産が報告された.今や 1個でも精子があれば挙児の可能性が開けている.今 後はより良い精子を確保,あるいは選別することの 重要性が増して行くことであろう.10年後の男性不 妊治療のあり方についても予測してみたい.

